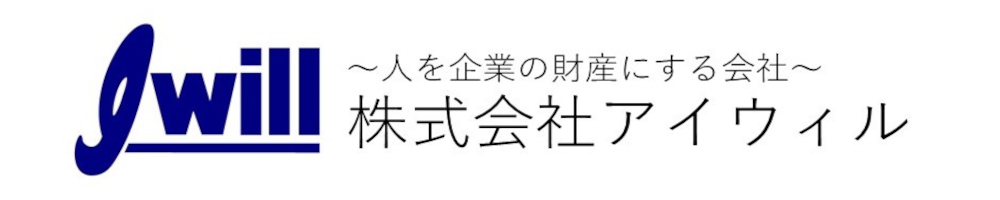染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 391」 染谷和巳
会社に補佐役はいるか
会社で社長につぐ二番、三番の序列は専務常務である。営業部長や製造部長から上がった人が多い。長年の労に報いる恩賞でなった人、助っ人として外部から招聘(しょうへい)された人もいる。大半の人が「あなたの一番大事な任務(役割と仕事)は何ですか」と聞かれて「それはこうだ」と答えられない。
消滅のダイエーが残した教訓
しばらく残っていただいだい色のマークやダイエーという店舗の名も今は完全に消滅した。
中内?のダイエーの盛衰を扱った小説やビジネス書がたくさんあるので詳細は省く。ここでは中内?の経営者としての致命的欠陥について述べる。(以下敬称略)
昭和三十二年(一九五七)、中内は神戸で薬局店を創業、安売りのスーパーで成功して店舗展開、コンビニエンスストアのローソンも開業して成功、わずか二十余年で一兆円企業となりフランスやアメリカにも進出、一大帝国を築き上げた。
拡大一辺倒の中内は後を振り返らない。土地を買って店を出し、またその土地を担保に次の店舗地を買う。新事業を起こし、既存の会社を買収する。多角化の道をひた走る。
社員や店舗の管理者や店員の教育は軽視、〝人材育成〟は念頭になかった。「経営は私とコンピュータとパートがいればいい」と言い放った。
こうした〝放漫経営〟がたたって会社は赤字になり翌年も赤字。赤字の額は増大し続け三期連続した。強気の中内もさすがに見過ごせず、昭和五十七年(一九八二)ヤマハの社長河島博を経営建て直しの副社長として迎え入れた。
河島の目には会社の欠点がはっきり見えた。不採算部門の切除と不採算店の閉鎖、新規計画中の事業の凍結を果敢迅速に行った。幹部教育、社員教育からパートの訓練まで時間と経費をかけて綿密に行った。
一年で黒字に転換した。翌年もその翌年も黒字が続いた。
「売上げがすべてを癒(いや)す」と言う中内には、ムリムダムラをなくす〝守備〟と社員の忠誠心や仕事意欲が実質的な売上げ向上に貢献するという「常識」が欠けていた。
昭和六十三年(一九八八)中内はプロ野球球団福岡ダイエーホークスを所有した。と同時にこの年副社長の河島を外部に出向させ、自分の長男を副社長にした。
中内?の再独裁経営が始まった。と同時に凋落が急速に襲いかかった。平成九年(一九九七)、長男を社長にし自分は会長になったが、経営上何の効果もなかった。
二〇〇〇年に入り毎年千人規模の人員整理、店舗閉鎖、ダイエーホークスなど所有する優良部門の売却と縮小均衡策で延命を計ったが及ばず。平成十六年(二〇〇四)産業再生機構の支援でイオン傘下に入った…。
創業者中内?は翌平成十七年八三才で他界。一代で事業に成功しその衰亡を見届けて死んだ。天才経営者の見事な人生だった。
中内は「生きかはり死にかはりして打つ田かな」の日本的経営を理解しなかった。五十年百年と何代にも亘って存続するのが会社であり、社長はそれを使命とし経営する。これが解っていれば「私とコンピュータとパートがいればいい」などとは冗談でも言うわけがない。
会社の創業から成長期までは有能な社長がいればいい。
二十年たち今後百年の存続を展望した時に有能な社長のほかにもうひとつ必要条件がふえる。〝補佐役〟である。
補佐役の仕事の範囲は広い。社長と共に走る伴走者、相談相手、裏の仕事の引受け人、時に社長に意見をする御意見番、社長が道を間違えていたなら諫言して対決するブレーキ役にもなる。
中内は「それ行けどんどん」では立ち行かなくなった時、河島を副社長にしその経営手腕を間近に見た。「わしのマイナス面を補って、それを数字の上で証明する腕前」を認めざるを得なかった。
中内は初めて力のある補佐役を得た。この男と二人三脚で進めば会社は健康に生き続けたろうに。
中内のようなワンマン社長には、好きなことを好きなようにできない苦痛は堪え難い。
会社が黒字化しても河島は自分の意見を言い、時には強く反対した。このうるさい目の上のたんこぶに堪忍できたのは三年。堪忍袋の緒が切れて、当時のダイエーに絶対の必要条件だった有能な補佐役を追放した。
これが中内の経営者としての致命的欠陥である。
耳に痛い事を言う人を捨てる
社長が「補佐役が必要だ」と本気で思うことが第一である。
会社を創って(あるいは先代から受け継いで)二十年、業界でも知られるようになり、金銭面でのゆとりもできてきた。
中小企業の中には初めから仕事を手伝ってきた奥さんや経理担当の女性社員が、補佐役という意識がないままに社長をうまく補佐しているケースが少なくない。他の社員の意見は聞かなくても、この人の言うことは無視できない。よく検討して判断しようとなる。この補佐役のおかげで大きい失敗をしないで済んだこともある。こうした人を持つ社長は幸運である。
ある会社。社長のアイデアが当たって成長し、社員百五十人を越える販売会社になった。社長は知人から「天才だ」と言われて相好をくずしていた。
拠点が全国十ヵ所あるので本社で幹部会議を頻繁に開いた。会議は大体社長の独演会。二十人の幹部は拝聴し相槌を打つばかり。
その模範生は社長の友人で経理の責任者をしている専務。自分から意見を述べたことはないし、社長に指名されても、社長の言ったことを復唱して「私もそう思います」と答える。他の幹部もそれを見習って、自分の数字の発表と反省以外は黙って聞いている。
一人、統括営業部長の常務のみ毛色が変わっている。まわりからは「何にも専務」に繋げて「何でも反対常務」と揶揄されていた。
社長の頭からは改革案や新事業のアイデアが溢れ出た。それを会議で鼻高々に「どうだ」と聞く。
本業と関係ない創作料理店、人材派遣、不動産仲介、学習塾などの新事業を披露する。専務以下はうなずくが常務だけは反対する。常務の意見を参考に案を練り直したり、修正したりするのは三割程度か。疎ましくてうるさいので社長は常務を無視し発言を封じて議事を進めた。
社長はお気に入りの幹部を責任者にして新事業を行い、ことごとく失敗し、大損を出した。会議で照れかくしに「損害は微小、学んだことのほうが大きい」と笑った。生徒がほとんど集められずに終わった学習塾の場合、教室の賃料、宣伝費、人件費など一年間で一億円近く使ったが、社長と幹部責任者は口裏を合わせて「五百万円くらいの赤字」と報告して誰にも文句を言わせず済ませた。
社長を畏(おそ)れない常務が〝経営のガン〟である。社長は四国の小営業所の建て直しに常務を出向させ、売上げ目標を達成するまで幹部会議参加不要と告げた。
常務は会社を辞めた。
以後会社は常務の祟(たた)りでもあるかのように衰えて行き、十年後社長は病気で死亡、現在は最盛時の十分の一の規模で細々と生きながらえている。
ダイエーの小型版だが、同様の話は巷(ちまた)にごろごろしている。
せっかくの有能な補佐役を社長自身が殺してしまえば、会社の未来はまっ暗なのだ。
会社を支える補佐役を育てる
社長を表の経営者とすると補佐役は失敗の尻ぬぐいや汚い仕事もする裏の経営者である。
副社長、専務、常務といったナンバー2の中に補佐役がいれば問題ない。しかしこうした上級幹部の多くは長年の功労者や部門長の成り上がりで、会社の方向付けや戦略を練る経営者ではない。まして社長に引き立てられて今の地位収入を得ている。社長の失敗の尻ぬぐいはしても、社長を怒らせるような反対意見や諫言はできない。
本当の補佐役不在が会社の存続にどれほど危険なことか例をあげて述べた。
もし今いないなら作らなければならない。誰が? 社長がである。
三井財閥の祖三井高利の十訓の三に「各家の内より一人の年長者を挙げ、老八分としてこれを全体の総理たらしめ、各家主はこの命にしたがうべし」とある。社長のもとにベテランの老八分(大名なら家老)を置きその意見をよく聞けということ。三代将軍家光に臆せず意見して「天下のご意見番」と囃(はや)された(講談の中の話だが)大久保彦左衛門が会社にも必要だということである。
若い社員が会社や社長に反抗するケースがある。もしその文句に「会社をよりよくする」「会社を支える」「会社や社長の欠点短所を正そうとする」意図が含まれているなら黙殺してはならない。その社員は補佐役の資質を備えているからである。社長がそばに置いて育てる価値があるだろう。
外部から招くのもいいが、今いる上級幹部の中から補佐役を作る。社長には難しい。アイウィルの新研修『ナンバー2養成研修』がこの難問を解決する。