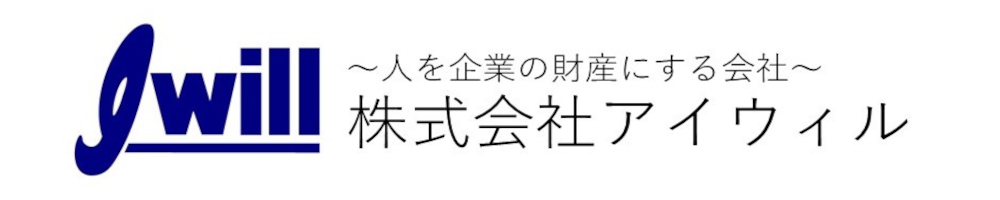染谷昌克の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 442」 染谷昌克
精神と行動を整える力
経営管理講座に何度か登場している京都のT先生。ヤアーッ8月号の「生徒が教師を評価する」を読まれ手紙をくださった。手紙には、授業はじめの挨拶は決まっていることが書かれていた。「時を守り 場を浄め 礼を正す」教育哲学者、森信三の言葉である。二〇年前のことを思い出した。
簡単にできることを徹底する
私に子供が生まれたとき、森信三の「三つのしつけ」と「立腰」を知った。講師をやり始めて「時を守り 場を清め 礼を正す」の言葉を知った。
三つのしつけは「子供にこの三つをキチンと教えれば、立派に成長する」と習った。
朝の挨拶をする。親に対し挨拶する。出会った人に「おはよう」「こんにちは」「さようなら」をきちんと伝える。
呼ばれたら「はい」とすぐ返事をする。返事は、相手を受け入れる姿勢。返事をしないのは「心ここにあらず」「我関せず」であり、誠実さに欠ける。
挨拶・返事は人間の根本的な姿勢である。
靴は脱いだら手で揃える。靴を揃えることは、単なる整理整頓の意味だけではない。生活の場を清める。自分の心を落ち着ける。小さなことを大切にする。誰でもできる簡単なことである。
こうした小さな習慣の積み重ねが、人を尊重する心を育て、社会生活の基礎になる。
森信三の言葉を借りると「靴を揃えられぬ人間に、大きな仕事はできない」という。
誰でもできるシンプルなことを子供時代から徹底することで、礼儀・誠実さ・自己管理といった「人間の根っこ」が育てられる。
森信三が提唱した「立腰」は、腰骨をまっすぐ立てて座る姿勢。見た目の姿勢を正すだけでなく、心の姿勢を正す教えである。
椅子に浅く腰かけ、寄りかからず背もたれから背を離す。腰を立てやすい位置に座る。骨盤を立てるイメージで、背骨をまっすぐに伸ばし腰骨を立てる。肩の力を抜き、自然に胸を広げる。深くゆっくり息を吸い、静かに吐く。姿勢が安定して呼吸が整う。
するとどうなるか。
形が心を支配し、落ち着きと集中が生まれる。姿勢を正す小さな習慣が、自分を律する力につながる。だらけた姿勢を防ぎ、勉強や仕事に集中できるようになる。
「時を守り 場を清め 礼を正す」
時を守ることは、時間の規律。約束の時間を守ることは、相手への敬意を示すと同時に、自分の生活を律する訓練でもある。時間を守れる人は、計画性と責任感を備え、周りから信頼される。自分を律する第一歩は、時間管理にある。
場を清める。身の回りの整理整頓は、心の乱れを整える基盤となる。散らかった環境は気持ちの緩みを生み、仕事や学びの集中を妨げる。場を清めることは、自分を律し秩序を尊重する姿勢の表れ。
T先生があえて「浄め」と書いたのは、精神を浄め整えるという意味を重くみているからだろう。
礼を正すことは、相手を尊重し、社会で調和的に生きるための基本である。挨拶や態度に表れる規律は、人間関係を円滑にし、信頼を築く土台になる。
「時を守り 場を清め 礼を正す」とは、自己管理・秩序ある環境・人間関係を、日常生活の中で養う教えである。
一九八〇年代アメリカの教育制度
一九八〇年代のアメリカの教育現場は荒廃していた。
全国学力調査でわかったこと。高校卒業生の約十三パーセントが日常生活レベルの読み書き計算ができない。英語で文法の誤りを修正できない、分数の割り算ができない高校生が多数。科学・数学分野での成績が主要先進国の中で最下位グループだった。
現場の問題は、授業が成立しないこと。
授業中の私語・居眠り・早退・無断欠席が常態化。教師への口答え、暴言、暴力事件も増加。生徒が廊下でタバコを吸う、酒や薬物を持ち込む、喧嘩が絶えない。
教師の権威の低下と士気の喪失も大きかった。
親からのクレーム・訴訟が多発し、教師が生徒を厳しく指導できなくなった。
体罰禁止が広がり、教師の指導・注意は必要以上に問題視された。
一九八三年の報告書『危機に立つ国家A Nation at Risk』には次のことが書かれていた。
・このままでは、外国の競争相手による経済的征服を招く。
・怠慢と無規律が、国家の基盤を蝕んでいる。
教育の荒廃は単なる学校の問題ではなく、国家の生存を脅かす危機だと位置づけた。
レーガン政権は「教師の権威と規律の回復」を大きな課題に掲げた。
問題解決は日本に学べ
世界最高水準の識字率を持ち、学力もトップクラスの日本。
日本の教育制度を学べ、とレーガン大統領は日本に教育使節団を派遣した。
日本の生徒が高い学力を維持している要因。学校内での秩序や生徒の態度の管理方法。教師の権威や教育に対する責任感の強さを理解する。
これらの目的のもと、アメリカの教育関係者は日本の学校を訪問し、教育現場の視察や関係者との意見交換を行った。
使節団は、日本の教育制度の特徴を学んだ。
文部省が教育課程や教科書を統一的に管理する。学習は生徒の自由ではなく「詰め込み式」
学校生活において、集団行動と規律が強調されていた。
教師が教育の中心として、生徒に対して強い指導力を持っていた。
これらの特徴は、アメリカの教育関係者にとって新鮮であり、特に規律の保持や教師の役割に関する点に注目した。
その後、アメリカでは日本の教育制度を参考にした改革が検討され施行された。
一九八〇年代の日本の教育は、「画一的・規律的」な反面、いじめや校内暴力が顕在化し、「ゆとり」「個性」へ舵を切り始めた。
アメリカが「規律の回復」を叫んでいた同時代に、皮肉なことに日本は「規律の緩和」と「個性尊重」へ向かっていったのだ。
森信三は規律を教えてくれる。日本の教育制度の根幹の教えである。規律があるから組織に秩序が生まれる。秩序の中で自由や個性が発揮される。
現在の日本の教育現場は八〇年代のアメリカと似ている。若い世代の責任ではない。能力に関しては四〇年前と比べたら、うんと高くなっているだろう。企業が腹を据えて教育すれば、大きな問題ではない。
<経営管理講座バックナンバー>
- 2025/10 経営者養成研修
- 2025/09 黒ひげ危機一発
- 2025/08 やさし過ぎるは、悪なり
- 2025/07 組織を統(す)べる力とは何か
- 2025/06 経験で育てるか、教え育てるか
- 2025/05 社長も、部長も、みんな若者だった
- 2025/04 人材は〝人財〟か〝人罪〟か
- 2025/03 管理者としての上級任務
- 2025/02 歩き続ければ必ず越える
- 2025/01 歴史を繰り返そう
- 2024/12 三十一年の歴史に幕
- 2024/11 増えてくる甘ちゃん族
- 2024/10 予期せぬバトンタッチ
- 2024/09 かつての〝学問〟に戻る時
- 2024/08 手書きが思考力の基礎
- 2024/07 高橋先生から学んだ事
- 2024/06 作文に特化した授業を
- 2024/05 精神強化と意識改革を
- 2024/04 積上げてきた美の遺産
- 2024/03 美に対する感性を磨く
- 2024/02 修復できない大被害が
- 2024/01
魁 としての奮闘の記録 - 2023/12 恥と秘密があってこそ
- 2023/11 外人と共生する社会か
- 2023/10 中国に魚は売りません
- 2023/09 捨てたものを見直す時
- 2023/08 経済で解決できない事
- 2023/07 悪運強し四七歳失業者
- 2023/06 有能でもNo2失格の男
- 2023/05 失敗が生んだ教育手法
- 2023/04 新会社を成功させたが
- 2023/03 私事よりも仕事を優先
- 2023/02 二十代は苦労勉強の時
- 2023/01 仕事と人間に恵まれて
- 2022/12 上司に頼られる社員に
- 2022/11 失敗と挫折は成長の糧
- 2022/10 たまには恥と失敗話を
- 2022/09 騒がせ屋の民主的小言
- 2022/08 昔通った道にまた来た
- 2022/07 自己啓発による勉強法
- 2022/06 甘えるな!甘やかすな
- 2022/05 勝利の方程式を作る人
- 2022/04 強く賢くやさしい人に
- 2022/03 しつけと指導の復権を
- 2022/02 歴史から何を学ぶのか
- 2022/01 歴史を学び新聞を読む
- 2021/12 大局観と先見性を磨く
- 2021/11 〝守り〟についての考え方
- 2021/10 居なければ探し育てる
- 2021/09 ナンバー2研修の意義
- 2021/08 会社に補佐役はいるか