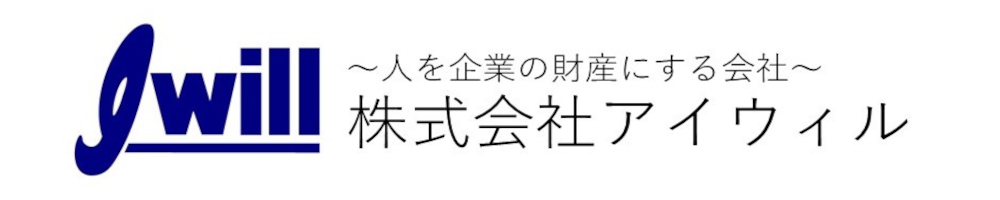染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 408」 染谷和巳
仕事と人間に恵まれて
小企業には目から鼻に抜けるような〝切れ者〟はいない。澄まし込んだ秀才もいない。〝おもしろい奴〟はたくさんいる。二十代は仕事の腕を磨く時であると同時に、人間修行の時である。おもしろい人に数多く接すれば自然と「人を見る目」が養われる。それは指導者になった時役に立つ。
二年半の底辺の経験が生き
この〝取り屋〟の鞄持ちは、穴掘り人夫と同様の新鮮な体験だった。
新聞、雑誌の中には会社の秘密や欠陥の情報を得ると、会社を脅して「広告料」をせしめる媒体がある。今はネットである。「ブラック企業だ」と騒いで、会社がそれなりのお金を出すと鎮まる。
〝総会屋〟という職業もある。株主総会で経営者が失敗や隠蔽を追求されると、そうした意見を妨害する。封じ込める。「議事進行を妨げる」といって反対者を会場からつまみ出すといった荒っぽいこともする。会社から謝礼金をもらう。暴力団の〝みかじめ料〟と同類だと思えばいい。
佐藤編集長の場合、過去にはそんなことをしていたのだろうが、今は政治活動はしていないし出版物も出していない。地域や会社に尽力も貢献もしていない。大ボラを大見栄を切って演じて、多少のお金を得ている。
会社はこうした得体の知れない相手に支払う金を予算として組み込んでいる。二万、三万円をけちって後で何をされるか解らないので準備してある。やってきた相手に年一、二回定期的に払っている。
編集長は長年これをやってきた。おそらく年間五〇?百万円の収入になっているのだろう。
荒田を連れて行ったのは〝大物〟としてハクをつけるためである。荒田はそれに利用された。
自分の師匠が小悪党だと解ったことと、会社が自己防衛のため細心の注意を払っていることが解っただけで貴重な体験だった。
麻布に戻って数日後、編集長は荒田を銀座のキャバレーに連れて行った。慰労のためもあるが、〝真剣勝負〟で疲れた神経を癒やすためもあったろう。その夜は紬の袷(あわせ)を着流してホステスに〝先生〟然と振る舞っていた。
いいものを作ることに執着する職人気質の編集者として尊敬していた。その尊敬の念がガタンと落ちた。
それが態度と行動にちらちら出たのだろう。編集長は荒田を注意せず、南田にあたった。荒田からよく見える畳の部屋で南田を罵り、打擲(ちょうちゃく)した。醜い光景だった。
次の仕事がこなかった。だから取り屋出張をしたのだが、荒田はすることがない。
〝渡りに舟〟とはこのことだろう。「すまい」の営業マンだった長井から電話があった。自分も辞めて小さい業界誌にいる。〝編集長〟を探している、来ないかという話だった。
素直にそれを編集長に言うと「修業になる、行きなさい」と許してくれた。
辞めて半年しかたっていないが「すまい」は廃刊、会社は解散したという。中橋は奥さんの父親が経営する印刷会社に入らず、マンションの専門誌に就職したという。
お茶の水の東京医科歯科大の裏の酒屋の二階に〝食品研究社〟はあった。
荒田は百ページ程の雑誌「月刊食品」の編集長になった。
雑誌は毎回農学博士の研究論文が載っているが広告主は漬物会社と佃煮会社と食品添加物の会社で、荒田はその関連記事を書いてまとめた。
漬物メーカーを取材に行った。車のついた大きい鉄箱の赤や紫の毒々しい液にきゅうりやナスが浮いている。袋やパック詰めの漬物は寒々しい工場でこのようにしてできるんだと印象深かった。
もう一つの雑誌「食品開発」も岡野という中年の編集長が一人で作っていた。
荒田と岡野と長井たち営業マン二人の四人はよく飲んだ。下の酒屋で一升びんと肴を買って宴会。それでは足りず、お互いの家に呼び合って飲んだ。うち三人は所帯持ち。内心は解らないが奥さんはみな歓迎して酒の肴を作って出してくれた。
三月、荒田に長男ができた。
電電公社の下請会社が潰れたのが二十三歳の八月。九月から雑誌社に勤めて転々として、今二十六歳。まだ二年半しかたっていない。
わずか二年半でよくこれだけのことができたものだ。若い時の時間は濃密で一日が長い、一ヵ月が長い、一年が長い。もう十年もたっているような気がする。誰でもそうなのだろうかと思った。
社長に頼られる存在になった
事務員に加藤さんという女性がいた。ニキビ面で出っ歯で下唇にいつも歯の跡がついている。二十八の独身女性だが、本人は自分がブスだと思っている。
荒田の欠点は我慢強過ぎることだといったが、もう一つ大きい欠点がある。〝口が悪い〟ことである。人を傷つけることを平気で言う。傷つけるだろうと考え及ばないで口に出してしまう。恨まれる。嫌われる。憎まれる。
朝、加藤が出社してきた。挨拶の後、荒田、「美人だねえ」。
加藤の目にみるみる涙があふれこぼれ落ち、口をへの字にしてドアから外へ出て行った。
美人だとほめられて怒る女性がいるとは思わなかった。
まわりの仲間が「荒田君、ひどいことを言うね」とたしなめた。
それまで荒田に親しく接していた加藤は、以後必要最小限しか口をきかなくなった。
社長は駒井という五十がらみの腹の出た男で貫禄があった。押し出しはいいが気が小さいようで眼鏡の奥の目は落ち着きがない。
荒田を名前で「新ちゃん」と呼んだので加藤以外の社員はみな「新ちゃん」と呼ぶようになった。
「新ちゃん、今度の熱海の司会やってよ」
雑誌の広告だけではやっていけないので業者を集めて〝勉強会〟を年四回以上行う。熱海などの温泉で一泊二日。夕方まで研修で後は宴会。多い時は五十人集まった。会費一人一万円。一泊三食付きで旅館代は昭和四十三年頃は四千円を切っていたので講師料を払っても十分利益が出た。
司会は岡野が担当していた。
岡野は社長に〝対等〟の口をきく。仕事はきちんとするがそれ以上のことは一切しなかった。会社のためなど思ったことはない。駒井社長とは全くソリが合わなかった。
荒田は司会を大きい失敗なくやり遂げた。それから毎回勉強会の司会は荒田になった。
文系軟派の荒田は食品添加物や化学調味料といった硬い材料を扱う雑誌を〝読んでおもしろいもの〟にした。スポンサーの評判がよく広告が増えた。
お金と仕事が回って忙しくなったので社長は編集に一人採用した。松木というのんびりした男で、仕事はまずまずであった。これが荒田に幸運だった。
せっかく落着こうとした矢先
岡野は大学や農業試験場に足繁く通っている。「食品開発」は学術誌に近い雑誌である。ナンバー2として社内で睨みをきかしている。代替えがきかないのが解っているので大きい顔をしている。給料は社長と同じくらいもらっている。
その岡野が荒田を気に入った。岡野宅にみなで遊びに行った帰りに「もらいものだが飲んでくれ」と言って荒田にレミーマルタンや高級ウイスキーを四本くれた。
荒田は高級な酒を無造作にくれる岡野を好きになり尊敬した。
「新ちゃんのおかげで月刊食品が伸びている。この調子で頼むよ」とおだてられた。この人と一緒にここでずっとやっていくんだと思った。
一年経ち桜の四月。佐藤編集長からまた声がかかった。
「今、月刊レジャーという雑誌の編集を任されている。他のもっと大きい仕事が入ったので辞める。後任に君を推した。私の代わりにやってくれないか」
荒田も職を転々としているが五十を過ぎて編集長はまだ落ちつかない。実用書の編集下請けから月刊レジャーという一般雑誌の編集長になり、まだ四号しか出していないのにまた他の仕事に変わるという。
編集職人にしては山っ気があり過ぎる。
満州国の建国大学を出た、日本経済新聞の記者をしていた、代議士○○の秘書だった等々、自慢気に語る経歴は〝証拠〟が一切ない眉唾物である。
荒田は「行きます」と答えた。
辞めると言うと社長と岡野は必死に引きとめた。「松木君が私の代わりをできます」と荒田は答えた。松木がいなければ辞める決断ができなかっただろう。
この三年の体験で学習したこと。
①上に認められる社員になる。そのため実績を上げ、まわりより抜きん出た存在になる。
②信頼する上司、尊敬できる上司、人生の師に出会えば幸運である。
③思ったことをそのまま口に出せば相手を傷つけることがある。
④社長がだめな会社はすぐ潰れる。しかしてそこで身につけた技能を生かして後に上昇する人もいる。