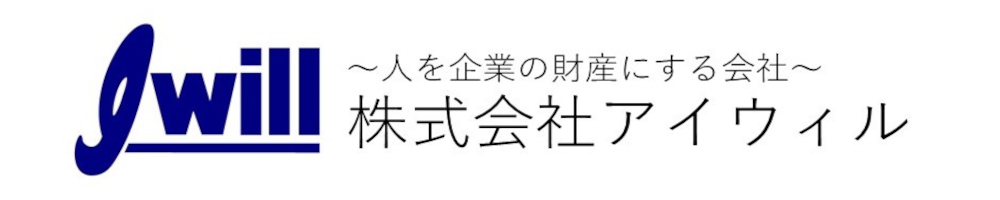染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 411」 染谷和巳
新会社を成功させたが
このところ〝終活〟のような話が続いているが、以前の辛口の論評や警句の講座に戻したほうがいいのではと複数の方から言われた。しかし偉そうなことを言う荒田が順風とはいえない〝経験〟をしてきたのを知って「私と同じだ」と共感してくれる社長もいた。もう二三回続ける予定である。
無料試聴制度で売上げ三倍に
㈱経営者教育研究所ができた。浜松町から徒歩五分の六階建てビルの四階に既に事務所は用意されており、社長の甥の経理の男と研究室から派遣された江藤課長が荒田を待っていた。
営業マンを募集。二十五歳以下の三人を採用。電話でアポイントをとっての訪問とダイレクトメールの引き合い客への売り込みが仕事である。荒田と江藤、それに新人の大野、呉(くれ)、正田の五人部隊。
ダイレクトメールの購入申し込みと問い合わせに応じるセールスの売上げが七〇%、営業マンの自力売上げは三〇%と低調だった。
重いカセットレコーダーを鞄に入れて営業に出る。一章十五分程聴いてもらっても、すぐには決まらない。労多くして益の少ない営業である。
男ばかり六人の職場。五時を過ぎると連日社内で酒盛りである。よく飲みよく歌いよく話した。
大野は力があり成績はつねにトップ、つぎが正田で呉は姿勢はいいが売れない。全く売れないのは研究室から来た江藤だった。
大野が荒田の講演を決めてきた。新聞販売店の社長五十人の前で「指導力」について話をすることになった。
三十三歳の初体験。上がってしまい何を話したか覚えていない。しかし質問が多く出て、別の地区でまたやってくれというリピートオーダーをもらった。
創価学会青年部の会合で話し慣れている大野が「語尾のネエが多過ぎる」「もっとゆっくり堂々と話したほうがいい」とアドバイスした。講師は大野のほうが向いていると荒田は思った。
ある時、大野と正田の二人を自宅に連れて来て泊めた。
泊める部屋などない。間貸ししていた老夫婦が引っ越して空いている四畳半の部屋があった。そこにふとんを敷いて泊めた。
空き間になってから荒田も入ったことがない部屋で壁が崩れ、唐紙が破れていた。季節が春で寒くなかったのは幸いだったが。
月末、二人が辞表を出して来た。
「取締役部長があんなひどい家に住んでいるのに驚きました。会社の将来に期待できません」。
八畳間で飲み食いした。そこを片付けてふとんを敷けばよかった。面倒がって、空き部屋があるのでそこに泊めた。後で荒田が入ってみるとほこりだらけで床も天井も荒れ放題の廃屋だった。
会社の将来を考えてではなく、こんな部屋に部下を泊める無神経な上司にはついていけないと辞表を出したのだろう。
新たに三人営業マンを採用。大野と正田ほど力がない。呉は二人の後を追って辞めた。
先輩の江藤課長は部下を育てられず窮していた。その窮鼠(きゅうそ)が猫を噛んだ。
今までも購入を決めてくれないお客様にカセットテープを一、二本預けることはあった。それを聴いてもらって判断してもらう。断られたらそのテープを返してもらう。
江藤は新品一セットの「無料試聴」を提案した。DMの引き合いは地方のほうが八〇%である。営業は遠隔地の引き合いに一軒一軒出張していたら割に合わない。
DMに「試しに聴いてみたい」の欄を作る。電話でアポイントメントをとる代りに「一セット送りますので聴いていただけますか」と試聴の許可をとる。
十二万五千円の商品をただで送るのだからネコババされる危険がある。テープをコピーしてしまい、商品を知らん顔で送り返してくる会社もあるだろう。
実際はそんなことをする会社は一%もない。会社は信用で成り立っている。もしそんなみみっちい汚いことをしたことが明るみに出れば失う信用は測り知れない。
内容の優れた教材なので聴いてくれれば買ってくれる。
荒田は「やってみろ」と江藤に言った。
ちょうど大衆キャバレーハワイが全国に店舗展開している時だった。中途採用の即席経営者の店長はホステスや従業員の指導に自信がなかった。
そこへ「これが指導者だ」が届いた。すぐ購入して幹部で聴いて勉強した。
一ヵ月二十セットが四十セットに倍増、翌月は六十セット。
重い鞄を持ち歩く営業は終った。
電話で無料試聴をお願いするパートの女性十人を採用。だめな営業マンが自動的に係長、主任になった。大野と正田がいてくれればと荒田は思った。
一般企業でも購入客が増え、千八百円のテキストも十冊、五十冊と同時に売れた。
当時電話代は高く、市内は三分一〇円だが、東京大阪間は四秒七円、北海道や九州は四秒一〇円で、一ヵ月の電話代は四百万円を超えた。
パートの時給は五百円で十人の月給は百万円以下。荒田は電電公社に料金の割引きを願い出たが相手にされなかった。
プライバシー優先の専務常務
つぎの商品開発が急がれた。
荒田はまた社長の自宅勤務になった。
社長は梅屋敷の母親所有の家から引っ越したばかりだった。母親はパチンコ屋や飲み屋をして女手一つで息子と娘の二人の子を育てた。息子が学校を出て家具製造会社に就職したので、いつも歯医者で世話になっていた衛生士を口説いて結婚させた。会社が軌道に乗ったと知って一安心。自分はひとり古家に残った。
新しい家は多摩丘陵をならして作った団地にあった。一戸建ての分譲建売住宅で広い庭がついている。同じような構えの家がつづら折りの道に百棟も並んでいる。
荒田は新しい家の二階で原稿を書いた。社長は庭を掘り返したり、詰碁の本を見ながら基盤に石を置いたりしている。昼休み、荒田は百段の石段を降りて南平(みなみだいら)駅の近くの食堂へ行って昼食をとった。
社長は三島由紀夫の割腹自殺と労働組合に激しく攻められて精神に異常をきたして以来、四年間一度も会社に行っていない。パソコンやケータイはまだなく、ファックスも普及していなかった。報告連絡は電話と手紙に限られていた。時折専務が呼ばれて来るが、毎日顔を合わせる社員は荒田のみである。
正月の二日、社長宅で新年会が開かれた。幹部六人が呼ばれた。奥さんが作ったおせち料理がふるまわれた。社長が「毎年こういう形で新年会をしたい」と挨拶した。
若い営業課長二人は昨日飲み過ぎたようで元気がなかった。専務と女性の常務は途中で「来客があるので」と言ってそそくさと帰っていった。元気なのは荒田一人。夕方まで続いたが白けた会になった。この新年会は前から解っていたのだから、専務常務は来客などの例年の行事を変更して臨むのが常識だろうにと荒田は思った。社長宅での新年会はこれ一回で終った。
荒田は入社の面接試験を社長と常務と総務部長の三人を前にして受けた。本人に自覚はないが随分態度が粗野で横柄だったらしい。常務と部長は「こんな礼儀知らずは問題を起こすから不採用」と訴え、社長が「いいじゃないか」と言っても強固に反対したそうだ。
ずっと後になって総務部長と飲んだ時にこの話を聞いた。「あの時社長が荒田君を採用していなかったら、会社はこんなに大きくなっていなかったと思う」人のいい正直な総務部長が頭を下げながら言った。
「これが指導者だ」につぐ大作の「管理者の条件」の原稿が仕上がった。
録音は都心のスタジオで一週間かけて行う。ディレクターは荒田。バックグラウンドミュージックなどの音楽は元々作曲家の専務が担当。ナレーターは前作と同じ声優の中村正。ラジオやテレビのアナウンサーは棒読みで説得力がない。中村正は長い文章を読ませたら日本一のナレーターである。
新製品ができて浜松町の営業部は活気づいた。人が増え四階に入り切れず二階と一階を借りた。ダイレクトメールが効果のある時代で、販売促進部は毎月数万通を発送した。
荒田はまた首輪をつけられた
荒田はいつも社長のそばにいて対面で話しているので電話報告の習慣がなかった。
スタジオで録音中に電話が入る。「電話をくれ」という社長からの電話である。一段落して電話を入れると「状況はどお?」。急ぐ用事があるわけではない。現場の様子を知りたいだけ。心配ならスタジオに来ればいいのにと荒田は思う。
新製品ができて荒田は浜松町に戻った。やはり社長から頻繁に電話が来る。
二ヵ月後荒田はまた社長宅の勤務に戻された。