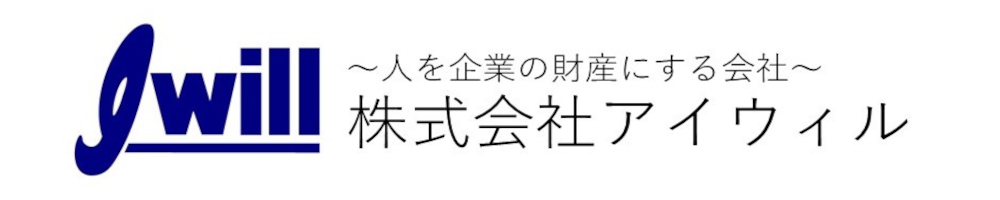染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 409」 染谷和巳
二十代は苦労勉強の時
「若い時苦労せんもんは使い物にならん」こんなカッコイイことが言える人がどれほどいるだろう。電信柱の穴掘り人夫から始まり小雑誌社を転々。二十八歳で就職した会社は給料が安く家族を養えない。金銭面で楽になったのは三十三歳になってから。荒田は十年間貧乏生活を送った。
会社を捨てて失踪した女社長
給料七万円。前の会社の二倍以上である。
編集は荒田一人。編集見習いを二人採用した。給料は二万五千円。それと比べても荒田編集長の給料は破格だった。
社名はユー企画。銀座七丁目にあり地下鉄日比谷線の東銀座が最寄駅。近くにビヤホールライオンやスエヒロがあった。当時スエヒロは上の階へ行くほど高級で地下は立食いの労働者食堂。荒田たちはそこで百円のすきやきランチをよく食べた。
社長は山本真理。容姿端麗。三十代後半か。クラブのホステスをしていたようだ。化粧が濃くヘビースモーカー。雑誌に一流企業の広告が多いのは社長の体当たりの営業による。
「月刊レジャー」は一八〇ページ前後、趣味、旅行、スポーツなど遊びのすべてをごちゃごちゃに載せていた。広告以外カラーページはなく、写真グラビアページが八ページで体裁は地味。表紙は山や海や温泉の写真を貸写真屋から借りて使っていた。
外部依頼の原稿はほとんどなく、決まった画家の山岳風景画が二ページ載っているだけ。よって荒田は一八〇ページをほとんど一人で埋めなければならなかった。
取材には自分のカメラ(マミヤの蛇腹式一眼レフ)を持ち歩いて記事中の写真を撮った。
多摩テック(二〇〇九年閉鎖)のゴーカートレースでは選手が衝突して宙に舞う瞬間を撮ることができた。グラビア一ページに拡大して載せた。
社長は「よく撮れたわね」とほめて、昵懇(じっこん)の画家からライカを借りて「これを使いなさい」と荒田に貸し与えた。
三〇?五〇ページの〝特集〟は温泉ランキング、日帰りのハイキングコース、遊園地一覧(ディズニーランドなどの大型施設はまだなかった)など、ほとんど現地取材をせず、カタログ、雑誌、本を調べて作った。毎月締め切りに合わせて原稿用紙をまとめる作業に追われた。「投稿欄の〝薄謝進呈〟を狙え」という特集は雑誌や新聞の投稿募集規定を二〇ページに亘りずらずら並べただけのものだが大当たりした。発行した五千部が売り切れた。こんな世知辛い企画がいいと解った。レジャー時代はまだ来ていなかった。
ある時社長が「四国に一泊二日取材旅行に連れて行くから準備してくるように」言われた。
朝出社すると社長が待っていた。しばらくして社長に電話があり「さあ、行くわよ」と荒田をうながした。外に車が待っていた。
運転席にでっぷりした中年男がおり社長は助手席、荒田は後の席に乗った。
二人はずっと喋っていた。
経理と電話番をしているおばさん(女子社員とは言い難い)は何でも知っていて荒田に教えてくれていた。
社長は雇われ社長でオーナーは友田という海草原料の化粧品メーカーの社長だという。社名のユー企画のユーは友からとった。「電話で声を聞いたことがあるが顔は見たことがない」とおばさん。
銀座の化粧品会社ということで田舎の化粧品店は商品を置いてくれる。中国四国九州に客が集中している。年二度、注文取りと代金回収に回っている。
この年(一九六八)東名高速が開通し名神高速とつながった。友田は東名を走ってみたかったのだろう。それで商売と取材を兼ねた不倫旅行(社長は独身だが友田は家庭持ち)を考えたのだ。
四国の吉野川上流の大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)に行った。二人はドライブインでお茶を飲んでいる。荒田はライカで写真を撮りまくった。
取材はここ一ヵ所、友田は三軒化粧品店を回った。帰りは後部座席で荒田は寝ていた。
二十八歳になった十一月の初め、出社すると経理のおばさんが「社長が消えた」と言った。お別れの手紙と記念のペンダントを見せて沈んでいた。
荒田の机の引き出しには「四十八手」のネクタイが、助手にはやはりエロ絵の扇子が記念に残されていた。二十日分の給料はない。
社長の実家に電話すると母親が出た。事情を話すと知っていたようでおろおろ詫びた。「どうしてあんな子になっちゃったんでしょう」と泣いた。
荒田編集長は十一月号まで六号出してまた失業した。
辿り着いたのが教材制作会社
十月に二人目の子ができていた。すぐ就職しなくては。
味の素のPR誌を請負っている制作会社に入った。青山の古い木造二階建ての家が事務所で看板も出していない。四、五人の男女が出入りしていた。
B六版五十ページの料理のカラー写真が延々と出てくる小冊子で、カラー印刷にたけた男が編集長、つぎに大きい顔をしているのがカメラマン、荒田のような文章書きの仕事はなかった。
入社一週間ほどして小山明子という女優が日本橋の料亭で料理を味わって感想を述べる特集の助手に連れ出された。
撮影が終るころ「車の用意をしてくれ」と指示された。荒田は道路に出てタクシーを止めて料亭前に待機させた。小山明子はすぐ出てきてタクシーに乗り込んだ。
ハイヤーを呼ぶべきではなかったか、タクシー代を女優に払わせていいのか。後で悩んだ。担当編集者はこの件で何も言わなかった。
これがこの会社で荒田がした唯一の仕事である。
皆、芸術家気取りで、一流ぶっていて鼻持ちならない。そこに荒田の出番は回ってきそうになかった。荒田は二週間で辞めた。給料は一円も出なかった。年の瀬、十一、十二月と二ヵ月給料なしは痛かった。
年末、新聞募集で社員教育研究所に応募。
社長が「月刊レジャー」の荒田の署名入りの紀行文を読んで気に入ってくれた。正月五日からの勤務が決まった。月給二万五千円(大卒初任給平均は三万円を超えていた)。
一月二十五日に荒田がもらった給料は一万数千円。ここ三ヵ月の総収入は四万円程だった。この頃から妻は長野の実家から月一万円の仕送りを受け始めた。荒田が現金書留の封筒を見てこれを知ったのは一年以上たってからだった。
当時「社員教育」は未熟な業界で、大企業や役所はアメリカの軍隊や工場で使われているテキストをアレンジして研修訓練を行っていた。
社員教育という言葉そのものが画一化や拘束のイメージで、自由と個性尊重の風潮に反していて、若い人が嫌う分野に属していた。
荒田もこの会社に何となくうさんくさいものを感じていた。しかし自分は〝文章を書く〟ことくらいしかできないと思っていたので、それが叶うなら、文学と縁遠いものでも給料が安くてもよしとしなければと思った。
ビジネス書、経済書も日本人が書いた優れたものは少なく、アメリカの翻訳ものが主だった。荒田が入社してから仕事のため読んだ本は九〇%がアメリカの翻訳本であった。
エミールを知らなかった社長
東京オリンピックが昭和三十九年(一九六四)。昭和四十年代は経営書、ビジネス書の黎明期(れいめいき)だった。よく読まれた日本の本は坂本藤良の「経営学入門」、一倉定の「あなたの会社は原価計算で損をする」、畠山芳雄の「こんな幹部は辞表を書け」くらいで、主流はアメリカの翻訳ものであった。
アメリカからテーラーの「科学的管理法」、スキナーの「行動科学」、ドラッカーの「目標管理」などの思考と手法が入ってきて、日本の経営者が学んで導入して行った。
管理者や社員はアメリカの自己啓発本を競って読んだ。
デール・カーネギーの「人を動かす」「道は開ける」に始まり、ナポレオン・ヒルの「思考は現実化する」、ブリストルの「信念の魔術」、レターマンの「営業は断られた時から始まる」などの翻訳書が書店の一等地を占めていた。
経営や社員教育に全く素人の荒田はこうした本をむさぼるように読んだ。
社長が会社を立ち上げる時に制作した営業マン向けカセットテープ教材「売上倍増への挑戦」はこうしたアメリカのビジネス書を下敷きにしており、文章は翻訳調のままだった。
ある時、荒田がルソーの「エミール」の話をした。どうすれば理想的人間を育てることができるかを書いた教育書の古典だと言うと、社長は「そんな本があるのか、読みたい」と言った。
社長は教育についてあまり造詣が深くないのを知って親しみを感じた。同時にこの会社なら自分の力を発揮できるのではないかと荒田は明るい気持ちになった。