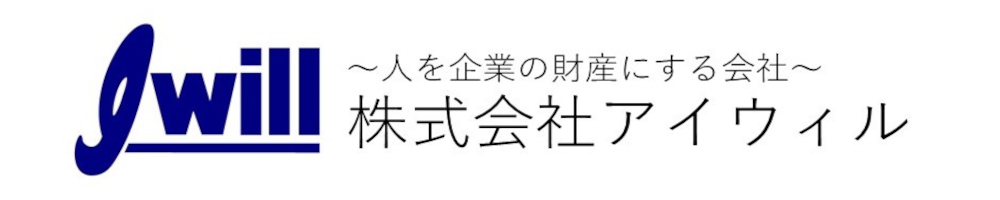染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 412」 染谷和巳
失敗が生んだ教育手法
数を当たれば荒田クラスの人材は見つかると思った社長は研究室を拡大し新人をどしどし採用した。おもしろい奴はいるが物になる人がいない。採っては辞め、採っては辞めの繰り返しが三年続いた。いろいろ工夫して訓練し教育した。誰も残らない。しかし〝訓練教育の手法〟が残った。
どうやって石ころを玉にする
日中だけだが荒田ひとりで社長宅の一部屋を占有している。子供がふえて部屋にゆとりはない。ここを研究室にするわけにはいかない。社長は新橋の研究室に出勤できない…。
社長の家から徒歩三十分の多摩動物公園駅から急坂を登りに登った明星大学のそばの一軒家を購入した。庭に池があり裏に前の住人が残していった金網のにわ鳥小屋があった。
営業から選抜した畠山、宮崎、寺松、ここで面接試験を受けて採用された榊原など総勢八人の研究室ができ、荒田部長の元に教材開発が行われた。畳の部屋にそれぞれが一人用のちゃぶ台を置いて原稿を書いた。
荒田は集中できなかった。部下が書いたものを読んで指導することに時間をとられた。社長は週一、二度来るが皆と雑談するだけ。自宅で新しいものを書きためている様子もない。
大世帯の研究室になってから優れた教材は一本も出なかった。「燃えよ営業課長」「指揮官」「殴り込み管理者」は荒田が一人で書き上げたが、ヒット作にならなかった。十年以上たってから「殴り込み管理者」は三甲㈱の後藤甲平会長が「経営者として行動の規範にした」と言い、武心教育経営塾の近藤建塾長が「今も教材に使わせてもらっている」と言ってくれたが。
昭和五十四年(一九七九)に教材開発会社から研修会社に大変身するまでの三年間に研究員を二十人近く採用した。みな数ヵ月で辞め、長くても一年である。国立市に第二研究室を設けたり、千葉県館山の〝民宿〟を買い取って研究別室にしたりもして、その都度人を採ったが、石ころばかりだった。
東大中退という男を採った。秀才然とした青二才で気位が高かった。中退の理由を聞いたが答えなかった。
同時入社の女性社員がのぼせあがり、男の気を引こうと言い寄った。女が自分と男との関係を漏らした。男を奪い合っていたもうひとりの新人の女が目を赤くして泣いた。
研究室中に知れわたり、荒田が社長に話すと社長は「へぇー」と言ったきり。男と女二人は入社二ヵ月もしないうちにほぼ同時に辞めた。〝東大〟にひかれて無条件で採用した荒田も二人の女と変わりない。
専務常務がいる営業本部は「研究室は遊んでいる。新製品ができないのに経費のむだ遣いが過ぎる」と荒田たちを白い眼で見た。
入っては辞めて行った約二十人の〝石ころ〟。確かにむだ遣いだった。しかしこの有象無象がまるでお伽噺(とぎばなし)のように最後には本物の光るダイヤモンドになった。
教材を作る研究員は文章力が求められる。いい文章を書くには頭の中に十分な知識が詰め込まれていなければならない。今までこの会社で合格点に達したのは荒田ひとりである。
社長と荒田は研究員の文章力を高める努力をした。書く力の前提に話す力、読む力をつけなければならない。その前に社会人として礼儀、挨拶と行動力それに忍耐力などの強い精神を養わなければならない。
研究員は〝文章を書く仕事がしたいから〟と入社してくる。
入社試験の作文すら書けない。この人をどうやって一人前の研究員に育てるか。まず話す、聞く、読む力をつける。その基礎となる挨拶、返事、相槌、復唱、メモ力を伸ばす。
さらに自分を変える、成長させる努力と苦労から逃げずに耐える精神力をつける。
人を育てることはできなかったが、どうすれば人を育てることができるかは解った。膨大な経費と時間を浪費させた、入っては辞めて行く石ころ研究員が教えてくれた。
三年後、会社が研修という商品を開発して奇跡的大方向転換できたのは石ころのおかげだった。
荒田の副業が会社繁栄に寄与
昭和五十二年、荒田が三十五歳の時、日刊工業新聞からコラム執筆の依頼があった。「管理者の条件」の著者は社長と荒田の連名だが、社長に頼むのは畏れ多いと思ったのだろう。社長に話すと「君ならできるだろう。請けてみろ」と許可してくれた。
八百字原稿用紙二枚の〝管理者講座〟が始まった。家で土日に書いて毎週郵便で送った。新聞の四面右上の目立つ場所だった。
一回の原稿料五千円、月四回で二万円はいい小遣いになった。四年半続いた。
もっと続く予定だったが、労働組合を批判する文を三回連続で書いた。新聞社の労働組合が編集の担当者に「許せん」と抗議した。編集は急遽連載を中止することにした。
評判のよいコラムだった。会社の社長が「愛読者だ」と荒田を尋ねてきた。新聞社にも読者から「なぜ突然中止した」という問い合わせが多数あったそうである。
編集者は単行本にして出版すると言ってきた。昭和五十六年、荒田四十歳の時「管理者の人間学」が出た。ベストセラーになった。印税が数百万円入った。
この一般書が会社に利をもたらした。
既に二年前の昭和五十四年に管理者対象の「地獄の訓練」が始まっていた。軍隊調の厳しい訓練との評判を得た。〝軍隊調〟を嫌う会社、嫌う社員は多かった。
この本が理論的根拠になった。
なぜ大きい声を出すのか。なぜ言語明瞭に話すのか。なぜキビキビ行動するのか。なぜ命令に従い報告するのか。なぜ規則規律を守るのか。なぜいやなことに耐えるのか。なぜ仕事の成果を上げなければならないのか。
訓練の課目の一つひとつの根拠がこの本によって理解できる。外面だけの軍隊調ではなく、頭脳と精神を鍛える研修であることが納得できた。
「あんな暴力団みたいな研修絶対行きません」と拒否する社員に社長や総務部長が「課長の君は部下指導と育成の能力が不十分である。その欠点を直す研修だ、行きなさい」と説得することができた。
訓練を担当する講師にとっても理論武装の頼りになる武器になった。研修参加をすすめる営業マンのセールストークの柱にもなった。
「人間学」に続いて毎年一冊計四冊が出版された。
大企業の経営者が「あなたの本を四冊セットにして新しく管理者になる人にプレゼントしています」と言ってくれた。
原稿料と印税も嬉しかったが、こうした読者の支持が何倍も嬉しかった。
初めの本が出た時社長が「印税いくら入るの」と聞いた。「二百六十
万円くらいです」と答えると「何だ、そんなものか、じゃいいか」と言った。多額なら会社の売上げにするか、特別に罰金を科すか考えたのだろうが、会社の研修の売上げは年二十億円に達しており「いいか」となったようである。
ある時研究室で庭の池を見ながら社長の奥さんが言った。「荒田さんの本読んで、〝ちくしょう、あいつ、何でこんな文章書けるんだ〟って口惜しそうに言っていましたよ」。
これもお金に優る名誉の勲章であった。この勲章が後に痛いトゲになるのだが…。
荒田は講師が務まらなかった
録音教材は一社で一セット購入してみなで学習する。そのため新しい教材の開発がつぎつぎなされなければならない。
研究室を充実させて新製品を間を置かずに出していく計画だったが、有能な執筆者が育たず失敗に終わった。
その失敗を生かして研修ができた。研修は一人いくらの参加料をもらう。管理者がみな受けた後も、これから管理者になる人の参加が見込める。効果のある研修なら一社何十人も出してくれる。
昭和五十四年、代々木駅前に教室を開き、通学式の研修を始めた。うまくいかず千葉県館山の研究別室を使って十三日間合宿の〝地獄の訓練〟を開始した。
第一回の講師は荒田が務めた。「地獄」という商品目に興味を持った週刊誌の記者が参加。「これでは極楽の訓練だ」と揶揄する記事を書いた。これを読んだ経営者が「それなら安心」と参加を決めてくれるケースもあった。
荒田は研修講師の仕事は向いていない、自分にはできないと思った。自分の不幸や痛みには我慢強いが、何度言っても言ったとおりできない生徒には我慢ならなかった。「こんなことがなぜできない」と怒る。生徒は萎縮し怯え、荒田を嫌った。
荒田の報告を聞いて社長もそれが解ったのだろう。荒田は降ろされ、畠山、寺松、榊原などの研究員が講師を専任するようになった。これが成功し研修参加者の数は毎月倍倍に増えていった。