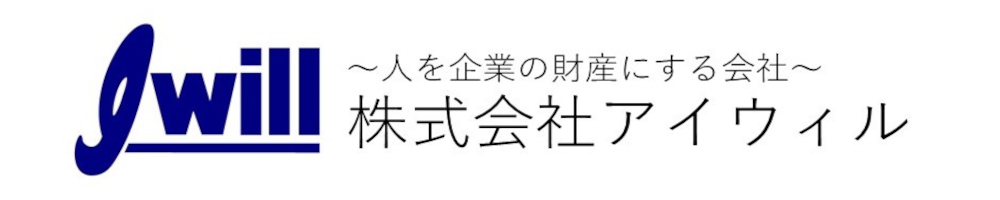染谷和巳の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 407」 染谷和巳
上司に頼られる社員に
いくら仕事ができてもそれを認めてくれる人がいなければ浮かばれない。荒田は幸運にもその人に恵まれた。雑誌の佐藤編集長。編集長は新人の荒田を〝見所あり〟と見て教え育て引き立てた。荒田はその期待によく応えた。二十五年間に亘り編集長はよくも悪くも仕事と人生の師匠であった。
穴掘り人夫から雑誌社勤務に
新卒五ヵ月で失業者になった。荒田は十一月生まれなので二年留年しているがまだ二十三歳。新卒扱いの就職先があった。
九月初め、新聞の募集欄を見て、飯田橋の雑誌社に入社した。
飯田橋駅から九段下へ向かう目白通りの右側にある木造家屋の二階が事務所。地下鉄九段下駅がまだなかったので飯田橋から歩いて通った。東京爆撃のせいか、道の右側は古い小さい木造家屋がびっしり並ぶ下町で、左側は高いビルのオフィス街だった。
荒田と早大卒二十八歳の中橋、青学卒二十一歳の奥村正子の三人が採用された。社長を含め七人の小世帯が十人になりにぎやかになった。
「ニュープレハブ」という月刊誌を出していた。プレハブ住宅が認知されつつある頃で、大和ハウス、永大産業、ミサワホームなどメーカー十数社がスポンサー。
新住宅の紹介とちょうちん記事が三分の二、三分の一は当時人気の雑誌「暮らしの手帖」をまねて実際に住宅の検分調査(取材)をして長所欠点を記し、優劣の採点評価をする記事だった。
住宅を買おうとする人にこれが好評で毎月五千部発行していた。住宅メーカーはここでいい点をもらうため広告を出稿した。
本作りから広告取りの営業までほとんどを編集長がした。編集長中心に動いている会社で、社長はいつも金策に出ていて会社にあまりいなかった。
編集長のそばに南田という女性がいた。編集長と名字が違うので夫婦ではないが一緒に暮らしている。二十年近く同棲している。子はない。この南田が編集長の手の回らない部分をよく補佐した。南田は潔癖症でミスを嫌い、大ざっぱな編集長の穴を完璧にカバーした。
編集長は「いいものを作る」が口癖で、お金と時間は度外視して仕事に没頭した。「俺が」という自己主張が強く頑固な職人気質の人だった。
編集長は若い人が好きなようで新人三人につきっきりで仕事を教えた。前からいる編集員二人は影が薄かった。能力が低く伸びが見込めない二人を見限って新人三人を入れたのだった。
荒田は仕事の覚えが早く、すぐ取材に出されそこそこの文章を書いた。中橋は「論文みたいなカッコばかりの文章を書くな!」と編集長に叱られていた。
〝頭角を現す〟とはこういうことを言うのだろう。三ヵ月後、荒田は五人の編集員のうち編集長が最も頼りにする存在になっていた。
入社五ヵ月、社内に不穏な空気が流れた。前の会社の最後の頃のあの空気に似ている。
通りの向かいに八階建てのビルがあり地下にランチもできる三十席以上の喫茶店がある。そこに新人三人が〝極秘〟で呼ばれた。
編集長と南田が待っていた。
「あの社長では会社が持たない。○○(新興住宅メーカー)の社長が住宅誌を創刊してもいいと言う。話がまとまった。五人そっくり受け入れてくれるという。どうだ?」
五人はその喫茶店の六階の広いフロアの新会社に移った。社長は住宅メーカーの社長婦人。何人かメーカーから連れてきたがあとは編集も営業も新規採用。二十人が揃った。
女優を表紙につかった「すまい」が創刊された。カラーページの多い豪華な雑誌。制作予算など気にしない編集長の方針だった。その分広告収入をふやせ! 営業部の努力もあってプレハブだけでなく大手工務店やマンションメーカーが広告を出してくれた。
荒田は〝編集キャップ〟という肩書きを与えられ編集長のそばの席だった。前は南田で左が中橋。
前の会社は雑誌の発行権は残っており元からの編集員もいたが、一号出しただけで廃刊になった。
ある日の夕方、前の社長がどなり込んできた。大声で悪口雑言を吐き続けた。編集長も社長も相手にしなかった。「訴えてやる」と言って出て行った。以後一度も姿を現さなかった。
中橋が奥村と婚約したことを公表した。
荒田が南田と二人だけの時に南田が言った。「前に奥村さんから荒田君とおつき合いしたい、荒田君が好きだと告白されたことがあったの。もう決まった人がいるようだから無理なのではと答えた。がっかりしていた。中橋君のことなんか全く出なかった。それが結婚なんておかしいわね」。
劣等意識の強い荒田にとって、自分も女性から好意を寄せられることがあると知ったのは革新的な出来事だった。
方針に従えず編集長は辞めた
二十五歳の三月荒田は結婚した。相手は事情を知らず関東宅内工事に入ってきた事務員で、ふつうは職場が長野になる時点で辞めるが、仕事場の飯田に実家があり、在宅勤務でよいということで残った。こんな偶然も人生にはある。
会社がなくなり荒田たちが散った後、二十三歳のこの娘も再度東京に出て事務機の会社に勤めた。荒田とのつき合いが深くなった。
結婚式には親戚や友人の他に編集長と中橋が出席した。
その五月、社長の仲立ちで中橋と奥村の結婚式が行われた。編集長、南田、荒田夫婦が出席した。中橋の親族は一人もいない…。
その後夫婦四人のつき合いはなかった。
以前、一度会社の下の喫茶店で四人で会ったことがある。奥村は荒田の結婚相手と話した。苦い思いをしたことだろう。
奥村は印刷会社の社長の長女で妹と二人姉妹。父親は露骨には言わないが、奥村は跡継ぎになれる男と一緒になろうと思っていた。
荒田を諦めてふさいでいるところを中橋が誘った。健康とはいえない青白い顔を好きになれなかったが、親も親戚もなく孤独に育ってきた話を聞くうちに同情して、結婚する気になった。荒田と顔を合わせるのがつらくて夫婦同士のつき合いは拒んだが──。
住宅雑誌は実用書である。ライバル誌はそれを心得て堅実な編集をしている。「すまい」は大型版で豪華でファッション誌のような仕上がりである。毎月一万部出していたが、返本の山ができた。
スポンサーの住宅メーカーは〝大船〟ではなかった。毎月の予想外の出費にあわてた。社長はカラーページの半減や表紙の女優使用の中止など制作費の削減を訴えた。編集長はきかない。事務所の隅の社長室から二人が言い争う大きい声が聞こえた。
一ヵ月後、編集長と南田が辞めた。編集長が大阪から呼び寄せた友人が代行になった。
その編集長代行は社長の言いなりになり、金をかけない雑誌に変えた。「すまい」は住宅メーカーのカタログになった。
今度は取り屋の鞄持ちの体験
それからしばらくして編集長から電話があった。
「そこはもうだめだ。実用書の製作で忙しいのでウチに来てくれ。中橋君に替わってくれ」。元部下全員に同じ話をしたようだ。
訪ねると事務所は麻布十番のアオイスタジオのまん前にあるアパートの一階で、ドアを入ると板の間の左右に二つずつ机が用意されており奥の六畳和室は編集長と南田の住居になっている。
荒田は移った。中橋は来なかった。実用書専門の出版社の依頼で「住宅の選び方」「日本の焼物辞典」などの単行本の編集をしていた。編集下請け業である。
単行本はレイアウト(割付け)が雑誌より単純で文章はパンフレット類を移し書きするようなものなので、荒田には楽だった。
二冊完成し出版社に納めた後のことである。「札幌に二泊三日出張する、一緒に行ってもらう」と言われた。
名刺を渡された。住所電話はアパートのもので、「政経懇話会麻布支部 秘書 荒田新」とあった。
「最近は行かないが以前は年三、四回回っていた」と言う。編集長の名刺には北海道出の元代議士の「秘書」とある。その代議士はもう故人になっている。その秘書をしたことがあると謳っている。
札幌。編集長は菊の紋様のバッチをつけ背広をリュウと着こなした堂々たる先生である。
相手は大企業の総務課長か部長。
自分がどんなに北海道の開発に貢献しているかをとうとうと述べる。それは御社の利益にもつながっていると…。
総務課長は心得ていて三万、五
万の「謝礼」を出す。
〝取り屋〟という職業である。編集長の裏の顔は取り屋であった。
何社も回ったある一社。封筒の中身が五千円だった。編集長は激怒し恫喝した。総務課長は萎縮した。「明日また来るから上と相談しなさい」と言って席を蹴った。
翌日荒田が一人で訪問して三万円入った封筒をもらった。