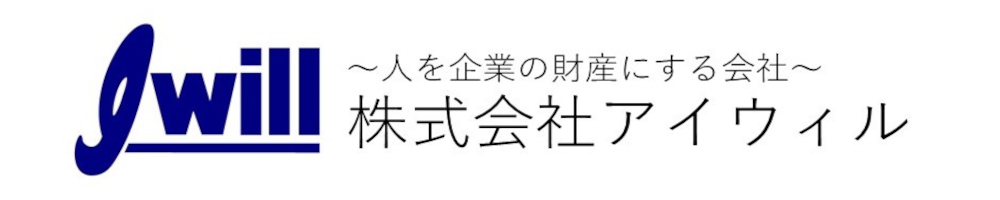染谷昌克の『経営管理講座』
人材育成の新聞『ヤアーッ』より
「経営管理講座 438」 染谷昌克
組織を統(す)べる力とは何か
「統率力」はリーダーシップのひとつ。「人をひとつにまとめ率いていく力」、これは上に立つ人間にとって魔法のような力。他人や組織から、借りることも貰うこともできない。一朝一夕で身につくものでもない。その人の、生き様や仕事ぶりから自然に生まれてくる力である。
高校生の真の統率者
東京都内の高校ラグビー部。チームテーマは主将が決める。「我」(が)がその年のチームテーマだった。
主将の秋井君に意味を聞くと「一人ひとりの個性、主張、意見をどんどん出していこう。うちの学校らしく楽しくやろう。という意味です。目標は花園です」と答えてくれた。
若者特有の個性尊重の自由主義。余計なお世話だが、それでラグビーというチーム競技が成り立つのかと、疑心を持った。
監督に聞くと「主将に任せています」と。主将は「それを僕がまとめて、強いチームを作ります」とのこと。お手並み拝見である。
このラグビー部は強豪校ではない。秋井君が主将になってチームが変わった。本気で花園を目指し始めた。プロのコーチを招聘(しょうへい)し、練習は今までの数倍きつくなった。高校の部活をイメージしていた新入一年生の中には、ラグビー部の本気度に恐れをなして逃げ出した部員もいた。
秋井主将自身のラグビースキルは高く、中学二年から東京都の選抜選手。中学三年生の時には全国で三十名の優秀選手に選ばれた。高校二年時点でラグビー強豪大学からスカウトがきた。
主将としては、部員への面倒見がよく、試合中はもちろんそれ以外でも、抜群のコミュニケーション能力をみせていた。部員だけでなく、監督、コーチ、マネージャーともコミュニケーションを欠かさなかった。
絶えず自分たちの進化した先のビジョンを語り、部員たちは目を輝かせながら聞いた。
練習も試合も、一番しんどいところに飛び込んでいった。ひるむ仲間には、叱咤激励した。
部員は明るい。表情はやる気に満ち、動きもよくなってきた。結果が出始めた。
全国選抜大会に招待された。初めての全国大会で勝利をあげた。七人制の東京都大会では準優勝。関東大会でもブロック優勝。花園の夢が近づいてきた。
秋井主将を三年間見てきた。主将になる前もなってからも、準備・後片づけは率先してやっていた。
自分の意見を押し通すのではなく、周りの意見に耳を傾けていた。
高校二年の時はケガと手術で半年間試合に出られなかった。その間コーチやマネージャーと一緒に、裏方仕事に従事した。監督との距離も一気に縮まり戦略戦術も共有できるようになった。グランド外からの声掛けが絶えず行われていた。
ラグビーが上手いだけでなく、徐々に仲間に信頼される存在になっていった。
それでも何かが足りなかった。東京都大会決勝で敗れ、花園への道は断たれた。
印象的だったのは、試合後選手たちが、秋井主将に群がり泣きながら謝っていた。「花園にいけなくてゴメン」と。
その光景を見て、慕われている以上の「この人のために」という真の統率者に対しての敬意を見た。
上に立つ人に必要なのは
染谷和巳が著書の中で言っている。
組織のトップや部門の長に求められる資質・能力はいろいろある。資質・能力の大元は何か。頂点は何か。一つに絞るとすれば何か。
今までの経験から導き出された答えは「統率力」である。
統率力といえば「リーダーシップ」という言葉が思い浮かぶ。ここではこの能力を際立たせるために「ガバナビリティ」(governability)を当てはめたい。
「ガバナビリティ」という言葉には統率力という意味はない。本来は「支配される人の従順さ」を表す。
「ガバナビリティが高い」といえば「人々が素直に従う」状態を表す。
この言葉が、日本ではなぜか統率力という意味で用いられている。「ガバナビリティに欠ける」は「統率力の欠如」の意であり、「ガバナビリティが高い」は「優れた統率者」の意味である。
これから統率力について述べるが、ここではガバナビリティの本来の意味を生かして、統率力を「人が心からつき従う力」と定義する。
「この上司についていく」「この上司の言うことを聞く」は、部下が判断して決めるものだ。もちろん上司が「ついてこい」といえば部下はついていく。しかし部下の心の中は、さまざまである。
「給料をもらっているのだからしかたがない」と思ってついていく場合もある。平和が続けば、部下はずっとついていくだろう。しかし、もし危険が目前に迫れば、上司を捨てて逃げ出す。この上司は〝統率力欠如〟である。
部下が上司を信頼し、尊敬し「どんなことがあってもこの人についていく」と思っていれば、イザというときに逃げ出すことはない。危機を打開するために懸命に働く。上司に認められ、喜んでもらうための努力を惜しまない。この上司は優れた統率者である。
はじめから統率力がある人はいない。統率力は、経験を積み、実績を残していくうちにだんだん身についてくる。しかし上司はそれを待ってはいられない。部下が素直に従わないなら、無理やりにでも従わせるしかない。逃げ出そうとする部下をひっつかまえ、あちらを向いている部下はこちらを向かせ、動かない部下は尻を蹴飛ばし、力づくで従わせる。そうしなければ目標を達成することはできない。
優れた上司はみな、この段階を経験する。部下の反発や抵抗に屈することなく、この段階を乗り越える。乗り越えて、〝部下が心から従う〟統率者に成長していく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
染谷和巳のいう〝統率力〟はどこから生まれるか。
それは〝圧倒的な当事者意識〟である。「この部門の成果も失敗も、全部自分の責任だ」と本気で思って動けるかどうか。企業の管理職が経営者に近いレベルの本気度・当事者意識を持った時、真の統率力が身につき始める。
前出の秋井主将は「統率力養成研修」で教えることを、自分の嗅覚で探り当て実践していた。高校ラグビーに本気で取り組んでいたのであろう。
秋井主将、昨年末にはU―(アンダー)十九の日本代表選手に選出され、桜のジャージでプレーしていた。
一方、秋井主将が卒業したラグビー部。七人制は二回戦敗退。関東大会予選敗退だった。
リーダー次第で組織は大きく変わる。
〝一頭のライオンに率いられた百頭の羊の群れは、一頭の羊に率いられた百頭のライオンの群れに勝つ〟のだ。
<経営管理講座バックナンバー>
- 2025/06 経験で育てるか、教え育てるか
- 2025/05 社長も、部長も、みんな若者だった
- 2025/04 人材は〝人財〟か〝人罪〟か
- 2025/03 管理者としての上級任務
- 2025/02 歩き続ければ必ず越える
- 2025/01 歴史を繰り返そう
- 2024/12 三十一年の歴史に幕
- 2024/11 増えてくる甘ちゃん族
- 2024/10 予期せぬバトンタッチ
- 2024/09 かつての〝学問〟に戻る時
- 2024/08 手書きが思考力の基礎
- 2024/07 高橋先生から学んだ事
- 2024/06 作文に特化した授業を
- 2024/05 精神強化と意識改革を
- 2024/04 積上げてきた美の遺産
- 2024/03 美に対する感性を磨く
- 2024/02 修復できない大被害が
- 2024/01
魁 としての奮闘の記録 - 2023/12 恥と秘密があってこそ
- 2023/11 外人と共生する社会か
- 2023/10 中国に魚は売りません
- 2023/09 捨てたものを見直す時
- 2023/08 経済で解決できない事
- 2023/07 悪運強し四七歳失業者
- 2023/06 有能でもNo2失格の男
- 2023/05 失敗が生んだ教育手法
- 2023/04 新会社を成功させたが
- 2023/03 私事よりも仕事を優先
- 2023/02 二十代は苦労勉強の時
- 2023/01 仕事と人間に恵まれて
- 2022/12 上司に頼られる社員に
- 2022/11 失敗と挫折は成長の糧
- 2022/10 たまには恥と失敗話を
- 2022/09 騒がせ屋の民主的小言
- 2022/08 昔通った道にまた来た
- 2022/07 自己啓発による勉強法
- 2022/06 甘えるな!甘やかすな
- 2022/05 勝利の方程式を作る人
- 2022/04 強く賢くやさしい人に
- 2022/03 しつけと指導の復権を
- 2022/02 歴史から何を学ぶのか
- 2022/01 歴史を学び新聞を読む
- 2021/12 大局観と先見性を磨く
- 2021/11 〝守り〟についての考え方
- 2021/10 居なければ探し育てる
- 2021/09 ナンバー2研修の意義
- 2021/08 会社に補佐役はいるか